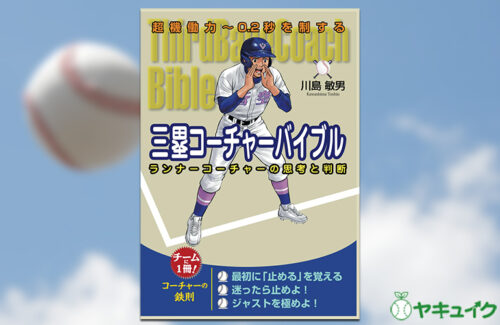(2018年4月19日の記事の再掲です)
取材に訪れたのは行田市でのスクール。会場は市の体育館で、毎週金曜日の18時をめどに練習がスタートするという。参加している子どもは小学校4年生から中学3年生までで、それぞれチームに所属しながらこのスクールに通っている。あくまで子ども達が「楽しむ」ことと「今まで出来なかったことが出来るようになること」が目的であり、試合に勝つことやその時に野球が急激に上達するということは主眼に置いていない。スタート時間も子ども達の集まり状況によってその時に応じて決めているという。その背景を佐藤さんはこう話した。
「子どもたちもやることが多くて忙しいんですよ。土日はチームの練習があるし、宿題や塾もある。そんな中で時間をきっちり決めてしまうとそれだけでストレスになりますよね。あくまで来たいと思って来てもらうことが大事なので、時間を決めて無理に来てもらうことは避けるようにしています」
実際にこの日も18時頃から徐々に子ども達が集まり始めたが、全員が揃うまでにはしばらく時間がかかった。そしてその間、佐藤さんからは特に何かを指示することはなかったのだが、子ども達は勝手にバスケットボールを持ち出してチームに分かれて試合を行っていた。練習が始まる前とはいえ、野球スクールにはとても見えない光景だが、これにも意味があるという。
「突き指するからとか、そんなことをやっても野球が上手くならないなどと言って、かたくなに他のスポーツを否定する指導者もいます。でも子どものうちに遊びや他のスポーツを経験することは将来的に野球にも生きてきます。子ども達もかなり汗をかいていますけど、単純に運動量も相当ありますから」
ようやく子ども達が揃ったのは18時半頃。ここからウォーミングアップに入っていったが、この時間を佐藤さんは重視しているそうだ。
「野球のチームの練習を見ていると、アップをちゃんとしないところが多いです。自分は引退した後、他の競技のことも勉強したのですが、体の使い方という意味ではアップは凄く大事だと思います。最近ではよく言いますけど、20年前から野球には肩甲骨と股関節の動きが重要だと思って、その動きを取り入れています。あと暴投したり打てない理由をつきつめていくと、真っ直ぐ立つことと真っ直ぐ横に移動することができないからというのが大きいです。バットとボールを持たない中で動きを覚えるというのがアップについてはテーマですね」

佐藤さんが話すようにアップでは腕を回したり、サッカーのブラジル体操のように足を上げたりする動作などあらゆる動きが取り入れられていた。そしてこのアップの時に子ども達を観察することを重要視しているという。
「アップを見ない指導者も多いですけど、自分はこの時に子どもの状態を見るようにしています。どこか痛い、何かがおかしいという子どもは動きや表情に必ず出てきますから。それに気づくという点でもアップは大事ですね」
アップが終わると佐藤さんから「今日は二人組で卓球」という声がかかり、次のメニューに移った。卓球と言ってもラケットで行うのではなく、グラブとボールを使ってグラブトスをしながら行う卓球に見立てたゲームだ。グラブさばきの柔らかさを養うことを目的としたものだが、これも野球の練習とは離れたものだった。

このメニューが終わると、次はゲーム形式の実戦。実戦と言っても紅白戦のようなしっかりしたものではなく、投手もじゃんけんで決め、ポジションもざっくりとした位置で守りながら行うもので、まさに昭和の子ども達が近所の空き地で行うようなものだった。最後に佐藤さん自身がトスを上げてバッティング練習を行いメニューは終了。『スクール』とは言いながらも、遊びの要素が非常に多いメニューだった。そして最も特徴的だったのが、佐藤さんがほとんど指示を出さないという点である。子ども達は勝手に順番を決め、ゲームでも自分たちで審判を行いそれに対して佐藤さんが何かを口出しすることは一切なかった。

「遊びに対して大人が口出しをすると一気に白けるんですよ。それに大人の顔色をうかがうようになる。それだと楽しくないし、自分で何かをやろうとするようにはなりません。だから自分は基本的には見ているだけです。それでも自然と上の学年の子が下の子の面倒を見るようになるし、ゲームも成立します。そうやって遊びながら楽しみながら野球を覚えていく。今の少年野球、中学野球は上のレベルを目指す子向けに偏っていると思うんですよ。そうじゃない子も野球ができる環境を作っていかないと本当の意味での底辺拡大にはならないと思います」
佐藤さんの話によると、取材を意識していつもより子ども達がしっかりやっているとのことだったが、それでも楽しんでいる雰囲気は十分に伝わってきた。このような取り組みが全国に広がり、一人でも多くの子どもが野球を楽しめる環境が整うことが本当の意味での底辺拡大に繋がる。そう強く感じるMFT野球スクールの光景だった。(取材:西尾典文/撮影:編集部)
取材に訪れたのは行田市でのスクール。会場は市の体育館で、毎週金曜日の18時をめどに練習がスタートするという。参加している子どもは小学校4年生から中学3年生までで、それぞれチームに所属しながらこのスクールに通っている。あくまで子ども達が「楽しむ」ことと「今まで出来なかったことが出来るようになること」が目的であり、試合に勝つことやその時に野球が急激に上達するということは主眼に置いていない。スタート時間も子ども達の集まり状況によってその時に応じて決めているという。その背景を佐藤さんはこう話した。
「子どもたちもやることが多くて忙しいんですよ。土日はチームの練習があるし、宿題や塾もある。そんな中で時間をきっちり決めてしまうとそれだけでストレスになりますよね。あくまで来たいと思って来てもらうことが大事なので、時間を決めて無理に来てもらうことは避けるようにしています」
実際にこの日も18時頃から徐々に子ども達が集まり始めたが、全員が揃うまでにはしばらく時間がかかった。そしてその間、佐藤さんからは特に何かを指示することはなかったのだが、子ども達は勝手にバスケットボールを持ち出してチームに分かれて試合を行っていた。練習が始まる前とはいえ、野球スクールにはとても見えない光景だが、これにも意味があるという。
「突き指するからとか、そんなことをやっても野球が上手くならないなどと言って、かたくなに他のスポーツを否定する指導者もいます。でも子どものうちに遊びや他のスポーツを経験することは将来的に野球にも生きてきます。子ども達もかなり汗をかいていますけど、単純に運動量も相当ありますから」
ようやく子ども達が揃ったのは18時半頃。ここからウォーミングアップに入っていったが、この時間を佐藤さんは重視しているそうだ。
「野球のチームの練習を見ていると、アップをちゃんとしないところが多いです。自分は引退した後、他の競技のことも勉強したのですが、体の使い方という意味ではアップは凄く大事だと思います。最近ではよく言いますけど、20年前から野球には肩甲骨と股関節の動きが重要だと思って、その動きを取り入れています。あと暴投したり打てない理由をつきつめていくと、真っ直ぐ立つことと真っ直ぐ横に移動することができないからというのが大きいです。バットとボールを持たない中で動きを覚えるというのがアップについてはテーマですね」

佐藤さんが話すようにアップでは腕を回したり、サッカーのブラジル体操のように足を上げたりする動作などあらゆる動きが取り入れられていた。そしてこのアップの時に子ども達を観察することを重要視しているという。
「アップを見ない指導者も多いですけど、自分はこの時に子どもの状態を見るようにしています。どこか痛い、何かがおかしいという子どもは動きや表情に必ず出てきますから。それに気づくという点でもアップは大事ですね」
アップが終わると佐藤さんから「今日は二人組で卓球」という声がかかり、次のメニューに移った。卓球と言ってもラケットで行うのではなく、グラブとボールを使ってグラブトスをしながら行う卓球に見立てたゲームだ。グラブさばきの柔らかさを養うことを目的としたものだが、これも野球の練習とは離れたものだった。

このメニューが終わると、次はゲーム形式の実戦。実戦と言っても紅白戦のようなしっかりしたものではなく、投手もじゃんけんで決め、ポジションもざっくりとした位置で守りながら行うもので、まさに昭和の子ども達が近所の空き地で行うようなものだった。最後に佐藤さん自身がトスを上げてバッティング練習を行いメニューは終了。『スクール』とは言いながらも、遊びの要素が非常に多いメニューだった。そして最も特徴的だったのが、佐藤さんがほとんど指示を出さないという点である。子ども達は勝手に順番を決め、ゲームでも自分たちで審判を行いそれに対して佐藤さんが何かを口出しすることは一切なかった。

「遊びに対して大人が口出しをすると一気に白けるんですよ。それに大人の顔色をうかがうようになる。それだと楽しくないし、自分で何かをやろうとするようにはなりません。だから自分は基本的には見ているだけです。それでも自然と上の学年の子が下の子の面倒を見るようになるし、ゲームも成立します。そうやって遊びながら楽しみながら野球を覚えていく。今の少年野球、中学野球は上のレベルを目指す子向けに偏っていると思うんですよ。そうじゃない子も野球ができる環境を作っていかないと本当の意味での底辺拡大にはならないと思います」
佐藤さんの話によると、取材を意識していつもより子ども達がしっかりやっているとのことだったが、それでも楽しんでいる雰囲気は十分に伝わってきた。このような取り組みが全国に広がり、一人でも多くの子どもが野球を楽しめる環境が整うことが本当の意味での底辺拡大に繋がる。そう強く感じるMFT野球スクールの光景だった。(取材:西尾典文/撮影:編集部)