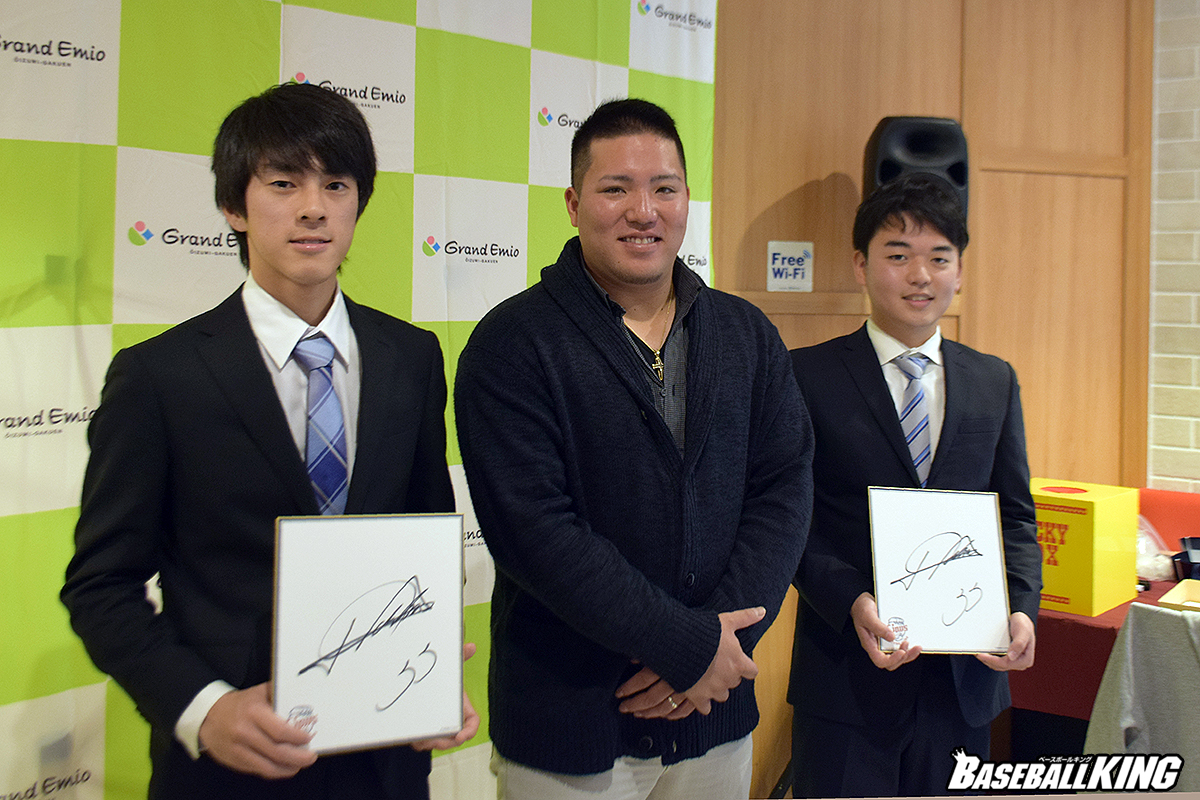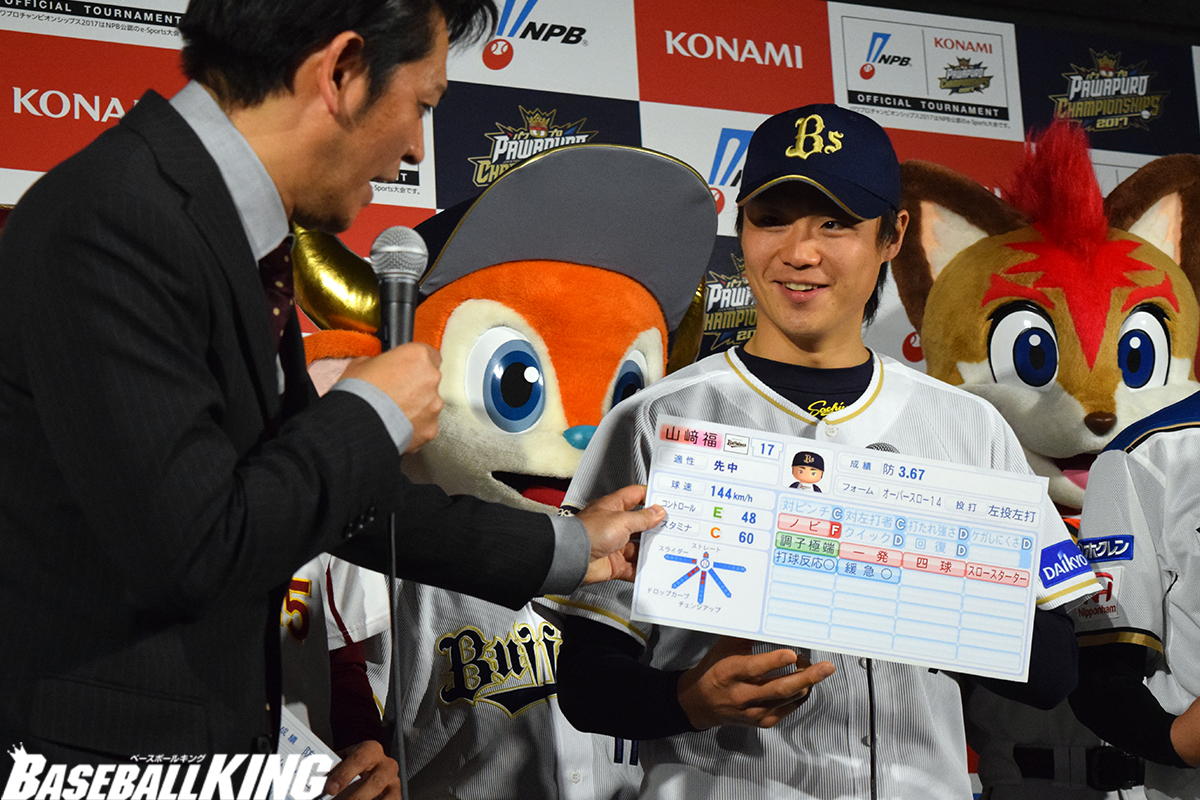◆ セ界2強時代
いまから10年前、セ界は巨人と中日の2強時代と言われていた。
2004年から中日監督に就任した落合博満と、2006年から巨人の監督に復帰した原辰徳。20数年前の現役時代、2シーズンだけ同じ巨人のユニフォームを着た両者だったが、原はFA移籍してきた元三冠王スラッガーに4番の座を奪われてユニフォームを脱ぎ、落合が80年代にどれだけ圧倒的な数字を残そうと、マスコミが大々的に取り上げるのはいつだって圧倒的な人気を誇る巨人の背番号8だった。
「人気の原、実力の落合」――。選手時代の立ち位置から、監督としての生き様まですべてが対照的な若大将とオレ竜。そんな両者が指揮を執った06年から11年の6シーズンに渡る“GD決戦”は球界を代表する好カードだった。
◆ ともに優勝3回、CSも互角
その6年間、リーグ優勝回数はそれぞれ3度ずつ。06年は中日も、07年から09年までは原巨人が球団36年ぶりのV3を達成。しかし、10年と11年は落合中日が球団初の連覇…。
2007年から開始されたクライマックスシリーズでも、ファイナルステージは4年連続で巨人と中日の対戦が続いた。07年と10年は中日が勝利。08年と09年は巨人が勝ち抜き日本シリーズへ。優勝回数に続き、CSも4年間で2勝2敗と全くの互角である。
当時の両チームには、80年代後半の王巨人vs星野中日とはまた別の殺伐とした雰囲気があった。優勝すると、読売新聞の手記で「(中日の)スポーツの原点から外れた閉塞感のようなものには違和感を覚えることがある」と珍しくかち食らわす原に、「俺がこの状況に手をこまねいていると思うか?見くびるなよ」と強気な姿勢を崩さない落合。このヒリヒリした関係は、当然オールスター戦のベンチでも続く。
元阪神監督の岡田彰布氏が自著『オリの中の虎』(ベースボールマガジン社)で明かしたところによると、落合、原、岡田と3人の監督がセ・リーグのベンチに揃った年に、落合が原に対して「巨人の次期監督は誰だ」とか「巨人はFAのあの選手に対して本当はいくら払った」とふざけ半分で嫌みを言い続けたという記述がある。
当然、言われた原は面白くない。大学時代からの知り合いである岡田に向かって「いったい何なんですかね」なんつって嘆くわけだ。(ちなみにそれに対する岡田の反応が「そんなん俺に言われても知らんがな」というのが三者三様のキャラクターを表していて興味深い)
◆ 異様な戦力充実度
この時代の中日といえば、のちにメジャーリーガーとなる川上憲伸とチェン・ウェインの両輪に、大ベテランの山本昌、09年と11年に最多勝を獲得する吉見一起といった豪華先発陣がそびえ立ち、ブルペンには盤石の浅尾拓也に守護神・岩瀬仁紀がスタンバイ。
正捕手は百戦錬磨の谷繁元信が守り、荒木雅博と井端弘和の“アライバコンビ”が二遊間でともに6年連続ゴールデングラブ賞を獲得。メジャー移籍前の福留孝介や、勝負強い森野将彦がクリーンナップを担っていた。
さらに、それぞれの時代でタイロン・ウッズやトニ・ブランコといったド迫力の外国人スラッガーが打線の中心に君臨。06年のウッズは47本塁打、144打点で球団記録を更新しての二冠獲得に加え、1シーズン4本の満塁弾と大暴れ。09年にそのウッズと入れ替わりで入団したブランコも、いきなり39本塁打でリーグ本塁打王に輝いている。
対する巨人も、06年オフの小笠原道大と谷佳知、07年オフのアレックス・ラミレスと立て続けにチームの土台となる大物の獲得に成功した。07年には高橋由伸がトップバッターとして自己最多の35本塁打と復活を果たし、全盛期を迎えつつあった阿部慎之助も球団捕手初の30発・100打点をクリア。
長年エースを務めた上原浩治やサウスポー・高橋尚成はアメリカへと旅立ったが、当時若手だった内海哲也を左のエースに抜擢。この時期のチームは“オガラミコンビ”に加えて、イ・スンヨプやセス・グライシンガー、ディッキー・ゴンザレス、マーク・クルーンと他球団の優良助っ人を立て続けに補強する一方で、04年ドラフト4位の亀井善行が25本塁打を放ったり、育成出身の山口鉄也や松本哲也もそれぞれ新人王獲得と若手も積極的に登用。原監督はまだ10代だった坂本勇人をショートレギュラーで使い続けた。
今になって10年前の映像を確認すると、当時の両チームの異様な戦力充実度が分かる。何人かの主力は後にメジャーへ挑戦。助っ人選手も含め、レギュラーの多くは当時の球界を代表する面々が顔を揃えている。
かつて、故・ジャイアント馬場は「ガチンコを越えたところにプロレスがある」という名言を残したが、あらゆるプロスポーツは感情が技術を超えた瞬間に名勝負が生まれる。侍ジャパンの常設化などもあって所属チームを越えた交流が盛んな現代には珍しい、グラウンド上のガチでマジの緊張感溢れる雰囲気が、GD対決を“平成の名勝負数え唄”にまで高めていたと言えるだろう。
◆ ベースにあったのは星野イズム?
落合監督が退任した翌12年、原巨人は日本一を含む史上初の五冠達成した。
ここから再びV3を達成するが、チーム力は主力選手の高齢化とともに年々低下。昨季は巨人と中日の2チームがともにBクラスで終わったが、これは1997年以来でなんと20年ぶりのこと。皮肉にも両球団とも一時代を築いた強豪チームにありがちな、世代交代のタイミングの難しさを痛感するチーム状況だ。
そして2018年、岩瀬や荒木は40代の大ベテランとなり、すでに一塁転向した阿部も39歳を迎える。ガッツ小笠原は中日で二軍監督を務め、逆に井端は巨人で一軍の内野守備走塁コーチと、10年前には想像だにしなかった未来を我々は目撃している。
振り返ると、この因縁のアングルは先日亡くなった故・星野仙一から始まっているのかもしれない。86年オフ、巨人への移籍が決定的と言われたロッテの三冠王男・落合を巡り「あいつが巨人へ行ったら勝てなくなる」とオーナーを説得。1対4の大型トレードを成立させたのが、中日の監督に就任したばかりの39歳・星野である。
闘将とオレ流、野球哲学は違えど“打倒巨人”のためにはそんなことは言っていられない。もしもあの時点で後のFAより7年早く落合が巨人へ入っていたら、オレ竜監督が誕生することもなかっただろう。それどころか、原と巨人監督の座を争っていた可能性もある。
「あいつだけには負けられない」と名勝負を繰り広げた原巨人と落合中日の仁義なき戦い。そのベースには昭和から平成へ時代を超えた星野イズムが脈々と流れていたのである。
文=中溝康隆(なかみぞ・やすたか)