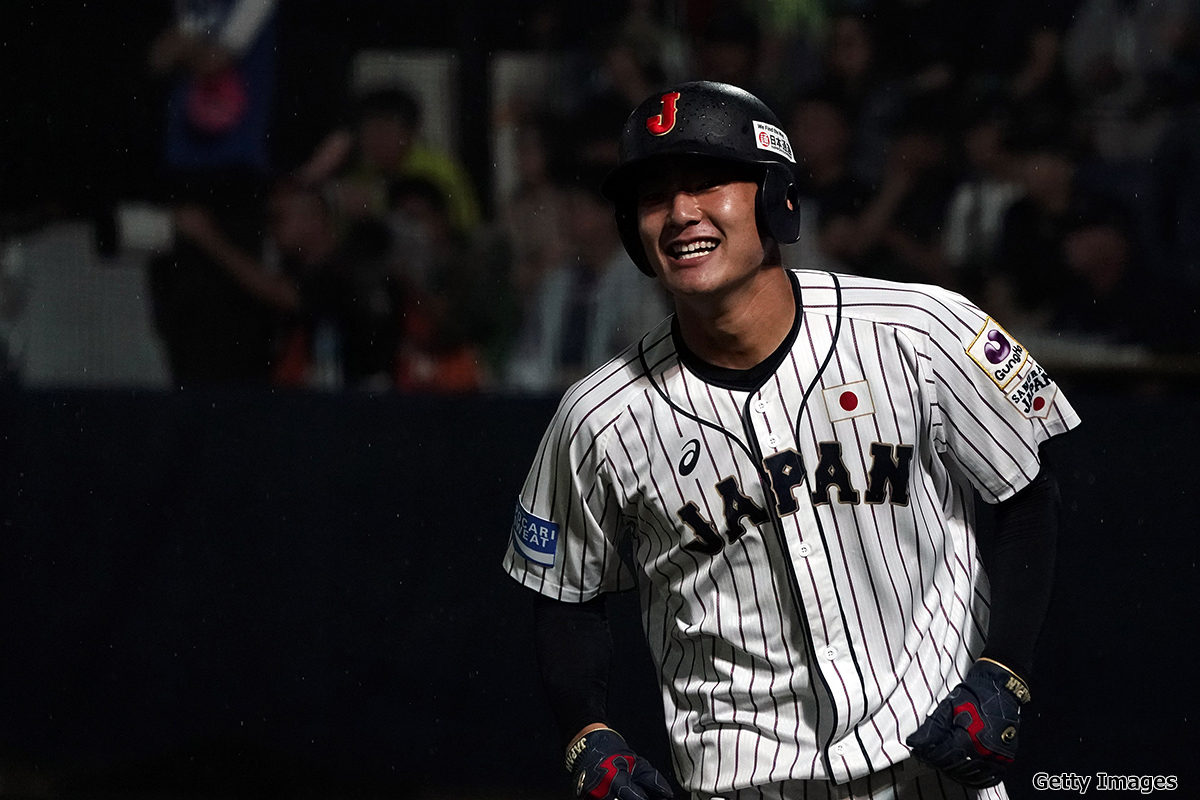◆ “隠し玉”ヒストリー【第5話:浅尾拓也】
2018年に34歳の若さで惜しまれつつ引退し、現在は中日の二軍投手コーチを務める浅尾拓也。甘いマスクから女性人気も高く、「浅尾きゅん」の愛称でも親しまれた。プロ通算416試合に登板して200ホールドを挙げた稀代のセットアッパーは、ドラゴンズのためにその細腕を振り続けた。
2010年に歴代最高となる47ホールドを記録すると、翌2011年には79試合に登板するフル回転で7勝2敗10セーブ・45ホールド、防御率0.41という、とてつもない成績を残して球団初のリーグ連覇に貢献。この年、セットアッパーとしては異例の最優秀選手(MVP)にも輝いた。
◆ オーラは“ごく普通の大学生”!?
そんな浅尾は、愛知にある日本福祉大から2006年の大学生・社会人ドラフト3巡目で中日に進んでいる。
当時、多くの野球ファンは「日本福祉大」という大学の存在自体を知らなかったはずだ。それもそのはずで、浅尾が入学した当初は愛知大学リーグの3部に属していた無名校だった。
浅尾は知多半島の常滑北高(現・常滑高)の出身。まったくと言っていいほど名前は知られていない存在だった。日本福祉大では、中部国際空港で清掃のアルバイトをしながら野球部に所属。プロなど、夢のまた夢の世界だった。
浅尾が入学したのと同時期に、社会人野球経験のある成田経秋コーチ(現・総監督)が就任。そこからサークルに毛が生えたようだった野球部は少しずつ強化されていった。チームは3部リーグから2部リーグへと昇格。浅尾は4年秋に1部昇格という置き土産を残し、大学野球生活を締めくくった。
4年時には最速150キロを超え、躍動感のあるマウンドさばきはプロスカウトから大いに注目されるようになった。だが、浅尾はどんなにスカウトが視察に訪れようと「僕なんかが本当にプロに行けるんですかねぇ」と信じられない様子だった。
日本福祉大・キャンパス内の食堂で爽やかな表情でインタビューに答える男からは、体育会系特有の威圧感が微塵も感じられなかった。身にまとうオーラはごく普通の大学生。そんな好青年が弱肉強食の世界で戦っていくと考えると、たしかに心もとなく感じたものだった。
◆ 「中日への恩返し」を胸に…
そんな浅尾には、どうしても進みたい球団があった。それが地元・中日である。まだ3部リーグで投げていた当時、浅尾をどの球団よりも早く発掘し、マークしてきたのが中日だった。
プロのスカウトから認めてもらえたことは、無欲の青年に上昇志向が芽生えるきっかけになった。どうしても中日に入って、恩返しがしたい……。浅尾は力を込めてそう語っていた。現在は意中の球団を口にすることはタブー視されているが、自由競争とはいえ誰よりも身近で見てくれたスカウトの世話になりたいと思うのが人情というものだろう。
ドラフト会議直前、浅尾を巡っては西武が上位指名するという報道もあった。浅尾は「中日以外から指名された場合は社会人に進む」と拒否姿勢を明らかにしていたが、不安は隠しきれなかった。ドラフトを目前に控え、精神的に不安定になることも多かったようだ。
それでも、大学生・社会人ドラフト当日は西武が指名を回避。中日が3巡目で指名して、浅尾は念願だった中日への入団を果たした。
浅尾がプロで見せた大車輪の奮闘には、「自分をプロに導いてくれた中日に恩返ししたい」という強い意志が根底にあったのだ。
文=菊地高弘(きくち・たかひろ)