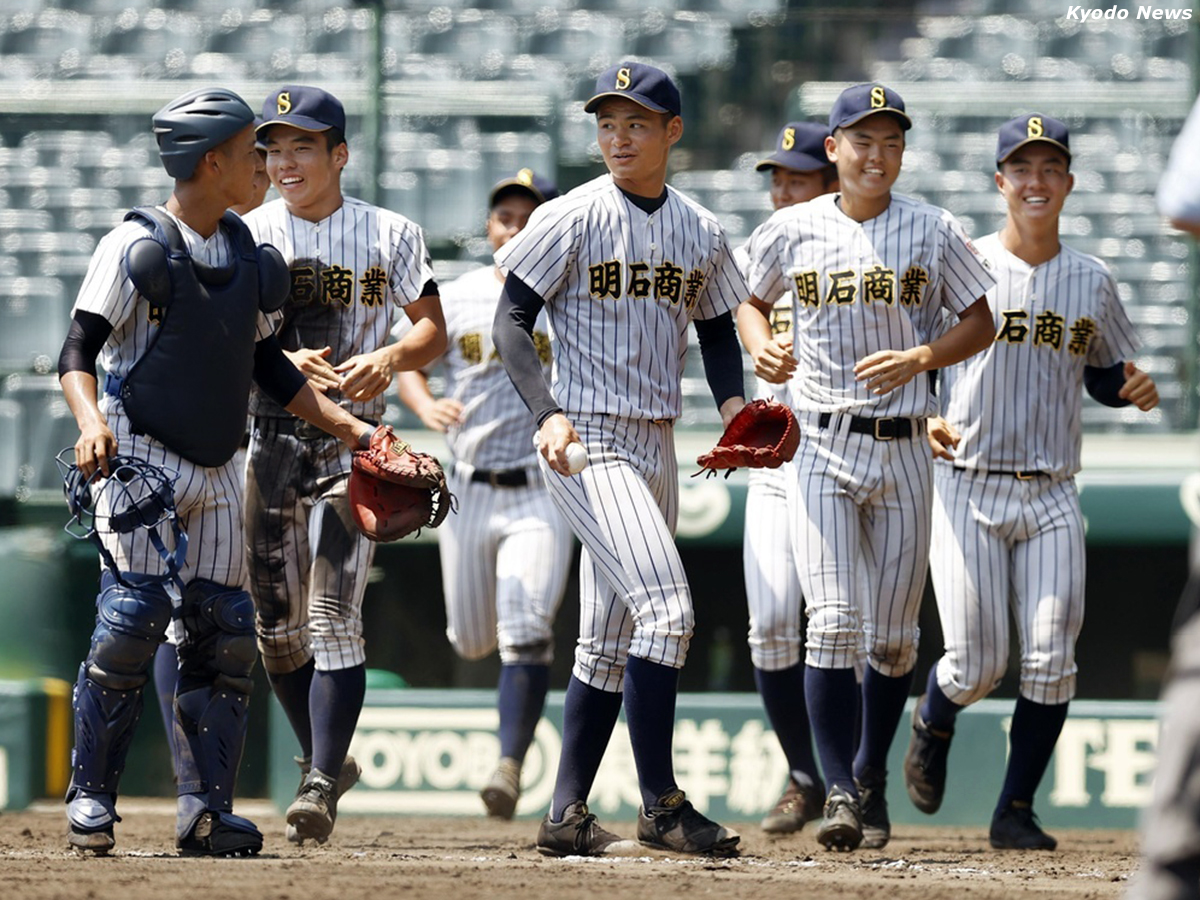◆ 白球つれづれ2020~第33回・心のキャッチボール
甲子園にセンバツ出場予定32校を招待した高校野球交流試合が17日、幕を閉じた。
各校の対決は1試合だけ、優勝校があるわけではない。ブラスバンドの大音量も、大地を揺るがす大声援が聞けるわけでもない。だが、出場した全選手が高校野球の聖地でプレーできる喜びに胸躍らせた。コロナ禍によって、センバツも夏の選手権も奪われた球児にとって、ようやくたどり着いた甲子園はやはり、かけがえのない場所だった。
プロ注目の中京大中京・高橋宏斗投手の153キロ快速球に目を奪われた。最終日に行われた大阪桐蔭と東海大相模の強豪対決は攻守にハイレベルな見応えある好ゲームだった。しかし、個人的には福島・磐城高校の戦いに最も熱い感銘を受けた。高校野球の原点を見た思いがしたからだ。
「1時間56分+7分、完全燃焼の夏」。ある新聞の見出しがすべてを言い表している。試合時間とそれに先立つ7分のノック時間。そこでノックバットを振るったのは木村保前監督だった。
◆ 空白の時を埋めた特別措置の7分間
昨秋の東北大会の善戦が認められてセンバツ大会に21世紀枠で出場を決めた。しかし、コロナによって大会は中止。この間に木村監督は県高野連事務局入りのため福島商へ異動が決まる。磐城高は県内屈指の進学校だ。甲子園出場という最大の目的も失い、かけがえのない恩師もいなくなる。この春、チームは一時、空中分解の危機にさらされたという。
そんな空白の時を埋めるように今回、特例措置として認められたのが木村前監督の“一時復帰”だった。
「IWAKI」のユニフォームに袖を通して与えられた時間はノックの7分。左利きのバットから速射砲のように放たれる打球は71本。
「どんな立場であっても子供たちをサポートできたことが嬉しい。まさか、こんな形で自分が同じユニフォームを着て、立てるなんていうことも考えられなかった」と語った50歳の前監督の目に涙が光った。
“魂のノック”の直後、磐城ナインは見違えるほどの輝きを放った。昨秋の東京大会優勝校・国士舘高を相手に一歩も譲らぬ白熱戦。3回には市毛雄大遊撃手が難しい飛球を好捕、7回の守備では一塁手の小川泰正選手がカメラマン席にダイビング、この回には一死二塁から右前打を放たれたが樋口将平選手が本塁に好返球でタッチアウト。8回にも清水真岳左翼手がダイビングキャッチのファインプレーと奇跡の守備が続いた。
「保先生の魂のこもった一球一球で最高の準備が出来た。自分たちもそれに応えて最後まで笑顔でやり抜こうと思った」と岩間涼星主将が振り返る。惜敗ではあっても、それほど前監督とナインの心はつながっていた。
◆ ひたむきに白球を追う球児たち
野球少年なら物心がついた頃から始めるノック。内野手なら足の運びやグラブさばきを覚え、外野手は打球の遠近感覚やクッションボールの処理も重要な教えとなる。加えて古くから言われるのが精神的なつながりだ。あと一歩、あと50センチに食らいつくことで球際の強さが養われ、いわゆる根性が身に就く。ノッカーと選手の「心のキャッチボール」といわれる所以である。
才能あふれる野球強豪校なら当たり前のように出来ることを、県立の進学校でも努力次第で実現できることを木村前監督は口を酸っぱくして唱え続けてきた。福島には県大会14連覇中の聖光学院のような高く険しいライバル校がいる。それでもあきらめずに練習に明け暮れたから、今回の甲子園の感動も生まれる。
高校野球の原点を見るような清々しさを磐城の野球に見た。ひたむきに白球を追う球児たちは口々に「甲子園は特別な場所」と言う。さらに岩間主将は木村前監督との濃密な時間を胸にこうも語る。
「将来は自分も指導者になって、磐城を甲子園に連れてきたい」。
1971年夏。磐城は「小さな大投手」田村隆寿を擁して準優勝に耀き磐城旋風を巻き起こした。あれから49年、わずか1試合の甲子園にも関わらず師弟の見事なつながりでさわやかな風をもたらした。
文=荒川和夫(あらかわ・かずお)