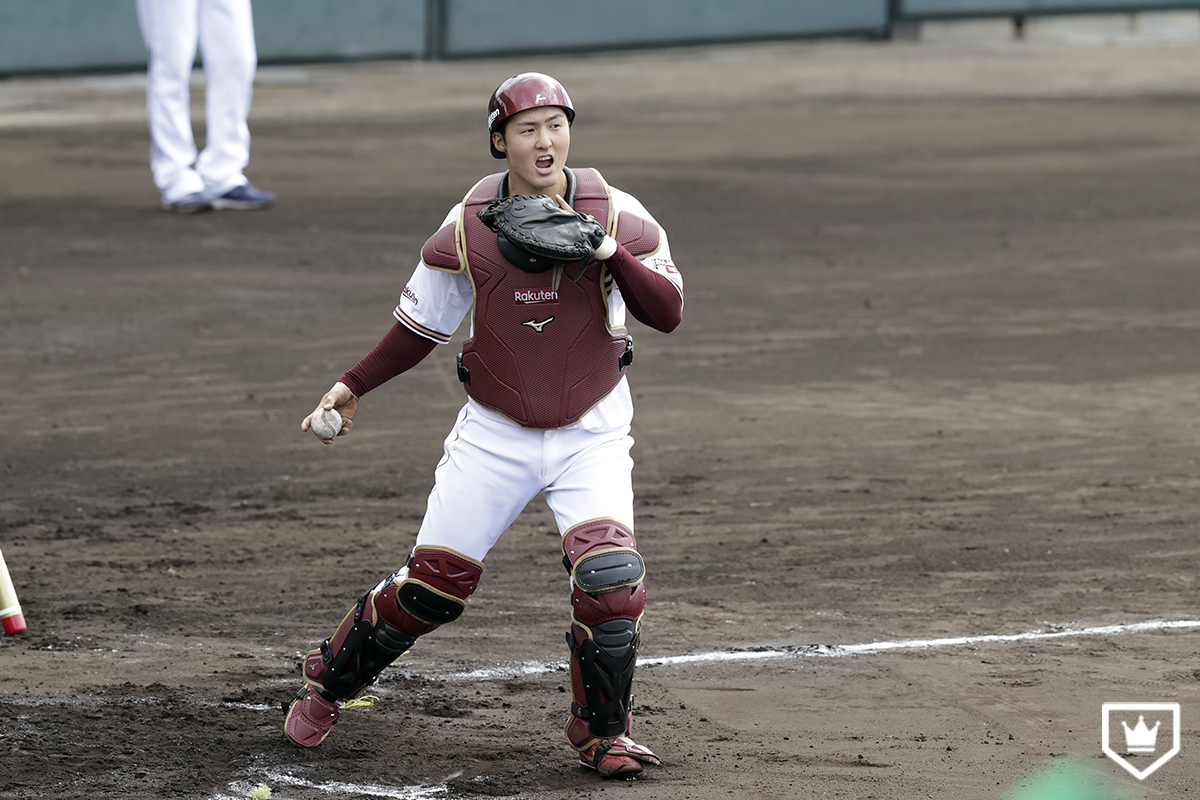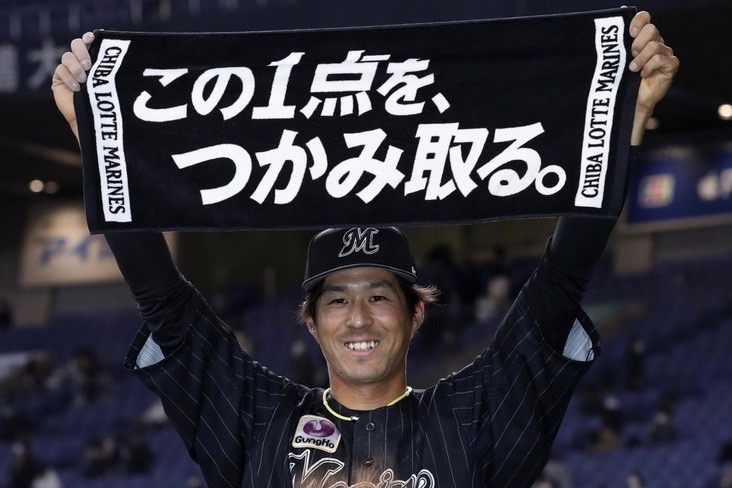◆ 白球つれづれ2021~第47回・赤ヘル軍団のはじまり
日本シリーズもたけなわである。
ヤクルト対オリックス。前年最下位から日本一の座を目指して上り詰めた両チームらしく、序盤は息詰まる熱戦が繰り広げられている。まもなく12月。現時点で勝敗の帰趨は明らかではないが、寒さを忘れさせる戦いは、どんなクライマックスを用意しているのだろうか。
日本シリーズと言えば、数々の名勝負を生んでいる。1979年の広島対近鉄の頂上決戦は“江夏の21球”として、今でも語り継がれている。
3勝3敗で迎えた第7戦。1点リードの広島は9回に無死満塁の大ピンチを迎える。マウンドには絶対的守護神の江夏豊。ここで近鉄のスクイズ策を見破り、後続も断って、劇的な日本一に輝く。古葉竹織監督の体がナインの手で宙を舞った。さらに80年、84年と3度のチャンピオンに輝き、名将は広島に黄金期をもたらした。
そんな古葉さんが今月12日に亡くなった。(発表は16日、死因は不詳)85歳。プロ野球退団後は晩年、東京国際大の監督を務めるなど、最後まで野球に愛情を注いだ人生だった。
“江夏の21球”から遡ること、4年前。古葉新監督の下で広島は球団創設以来初のリーグ優勝を手にしている。この年(1975年)は「赤ヘル・カープ」が誕生。広島の街が赤一色に染まったことでも、画期的なシーズンとなった。
同年はメジャー出身のジョー・ルーツ監督でスタートしたが、春先のゲームで判定を不服としたルーツ監督は退場をきっかけに退団。球団が後任に指名したのが古葉監督だった。
チームの快進撃と共に人気を集めたのが赤いヘルメットである。ルーツ前監督がメジャーリーグのレッズをイメージ。燃える赤でナインの闘争心にも火をつけようと採用したところ大きな反響を呼び、やがてアンダーシャツやストッキングまで従来の紺色から赤に統一してチームは生まれ変わった。
◆ 必然の変革
古葉監督の誕生時、チームは大きな変革期を迎えていた。
きっかけは68年から72年まで監督を務めた根本陸夫氏の時代にある。その後、西武やダイエー(現ソフトバンク)でも指揮を執った同氏だが、指揮官としてよりもチームの土台作りに長けた仕事師だった。この根本時代に後の中心戦力となる山本浩二や衣笠祥雄氏らが入団。コーチ陣には広岡達朗、関根潤三氏らを迎えて若鯉を鍛えている。後に広島市内の合宿所兼練習場である「三篠寮」には他チームが見学に訪れるほど、猛練習は日課となっていた。
ルーツ流メジャー仕込みの激しさも叩き込まれた中での古葉さんの登場である。彼もまた、数年前まで在籍していた南海でドン・ブレーザーコーチの提唱する「シンキングベースボール」の薫陶を受けていた。当時、南海の主力で兼任監督も務めた野村克也氏がヤクルトの監督就任後に掲げた「ID野球」の教科書にもなるほど高度な戦略、戦術である。
有望な若手が育ち始め、メジャー出身監督が戦う姿勢を植え付ける。そして古葉流のち密な機動力野球が席巻する。前出の山本や衣笠だけではない。高橋慶彦、山崎隆造、北別府学に大野豊ら、生きのいい若手が全国区の人気者に育っていく。黄金期の到来は必然でもあった。
常勝カープはファンの熱狂も呼ぶ。75年のチーム初優勝時の観客動員数は初めて120万人を記録した。前年が64万人余りだから、実に倍増だ。広島市の人口は当時100万人にも満たない。県内はもとより、中国地方や四国からもファンが押し寄せて、赤ヘル軍団に酔いしれた。街は赤一色。「野球は文化」を体現した好例でもあった。
◆ 優しさと厳しさと
古葉さんの人となりを振り返る時、多くの関係者は「優しさと厳しさ」を口にする。報道陣の前では柔和な笑顔を絶やさない指揮官だったが、一方では怠慢プレーなどには「口より先に足蹴りが飛んできた」と証言する。そして、一様に「今、自分があるのも、古葉さんのおかげ」と語る。これほど、監督冥利に尽きることもないだろう。
“江夏の21球”には、もうひとつのドラマがあった。無死満塁のピンチで広島のブルペンに目をやった江夏は、北別府と池谷公二郎投手の姿を見て怒りに震えた。
「何で俺を信用できないのか?」その矛先は古葉監督に向けられた。その異様さに気づいた衣笠がマウンドに歩み寄り、「お前の気持ちもわかる。辞めるなら俺も一緒に辞めてやるよ」と、なだめて大仕事を完結させた。
一時は感情的にもつれた江夏氏も、今では監督として当然の準備だったことを理解したうえで、こう語っている。
「自分に優勝の喜びを教えてくれた人。感謝しかない」。
名将・古葉竹織が亡くなり、現チームの主砲である鈴木誠也選手はポスティングでのメジャー挑戦を明らかにした。ひとつも、ふたつも時代は変わり、赤ヘルはまた新たな変革期を迎えている。
文=荒川和夫(あらかわ・かずお)