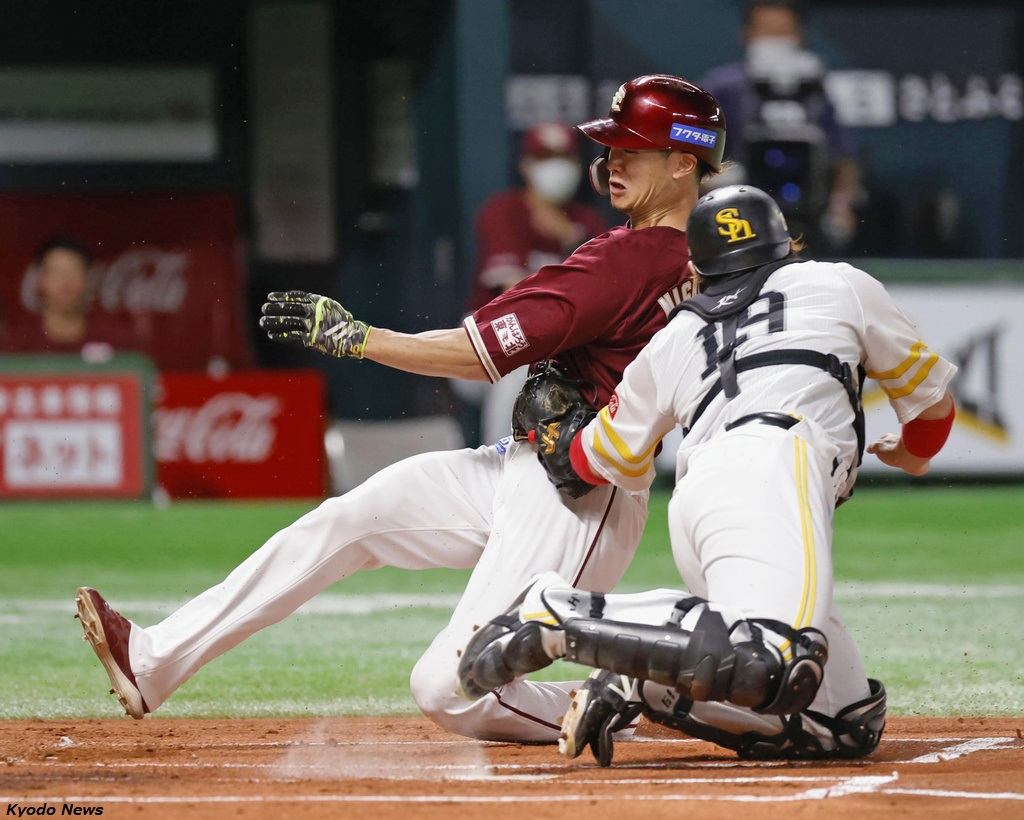◆ 「緊張しすぎて……」
なかなか一歩を踏み出せなかった。
PayPayドームで行われた7月26日の球宴第1戦。タイガースの青柳晃洋は人知れず“苦闘”していた。
「本当は1戦目に行きたかったんですよ……。さすがに緊張しすぎて行けなかった。早く行って喋る時間を長くしたかったんですけどね」
視線の先にいたのは、セントラル・リーグの指揮を執るスワローズの高津臣吾監督だった。
「小学校の時から見ていた選手ですし、こういう投げ方(変則投法)を始めてからずっと見てた選手だったんで。監督というよりはもう“高津選手”として見てたので、本当に(話しに)行けなかったですね」
小学生の頃から腕を下げてボールを投じていた“青柳少年”にとって、アンダースローから繰り出される宝刀・シンカーを武器にスワローズの黄金期を支えた絶対守護神は、憧れ以外の何者でもなかった。
シーズン中は敵将と会話を交わす機会なんてまず訪れない。キャリア初のファン投票で出場を決めた瞬間から、高津監督へのアタックを心に決めていたという。
「1戦目の試合前のブルペンで高津さんから“ちょっと見させて”と言って来てくれて。聞くチャンスだなと」
栄えある初戦の先発マウンドを託されていた青柳に早速好機はやってきたが、結局その日は会話できずに終わってしまった。
◆ 「憧れの人」から得たヒント
迎えた第2戦。背番号50はその背中を追いかけて走った。
「キャッチボール終わったぐらいに、高津さんがちょうど高橋奎二(ヤクルト)の所に話に来ていて、帰るところだったんですけど、走って追いかけて。そこで聞いて」
時間にして10分にも満たなかったが、青柳にとってはすべてが自身の進化と成長につながる内容だったという。
テーマはもちろん「シンカー」。青柳も一昨年から習得に励み、昨年は本格的に配球にも加えていた。
カウント球だけでなく、勝負球に使えるまでに精度も上がったものの、課題はスピード。緩く抜いたような理想のシンカーを投げていたのが、現役時代の高津監督だった。
互いにボールの握りを見せ合っての意見交換。「僕の投げ方だったら、中指の人差し指側にかけて投げるんですけど、それで抜くのはすごく難しくて。高津さんは中指の外側、薬指側にかけると言っていた。それでああやってポンと抜ける。握りの浅さで球速も変わりますし。高津さんは本当に縦に落とすイメージ」と振り返る。
同じ球種でも、リリースの違いで全く別の顔をのぞかせるシンカー。
「(緩いシンカーは)これから成長するにあたって覚えなきゃいけないボール。右バッターに遅いシンカー、入ってくるボールがあればツーシームも生きると思う。成長していく余地があるとずっと思っていた中で質問できたので良かった」と、球界最高の使い手から授かった“極意”に表情は緩んだ。
「高津さんは僕の憧れの人。ライバル球団の監督とか関係なく、憧れの人に質問にいけたという感覚。純粋に答えてくれましたし、本当にためになる話ばかりだった」
シーズンに入れば、首位を独走するスワローズ、ひいては敵将を苦しめていかなければならず、意見交換をするような空気は皆無になる。
4月から「無双」と言える快投の連続ですでに12勝を挙げ、猛虎のエースへ歩を進める青柳。“束の間の休息”で更なる高みへ駆け上がるためのヒントを得た。
文=チャリコ遠藤(スポーツニッポン・タイガース担当)