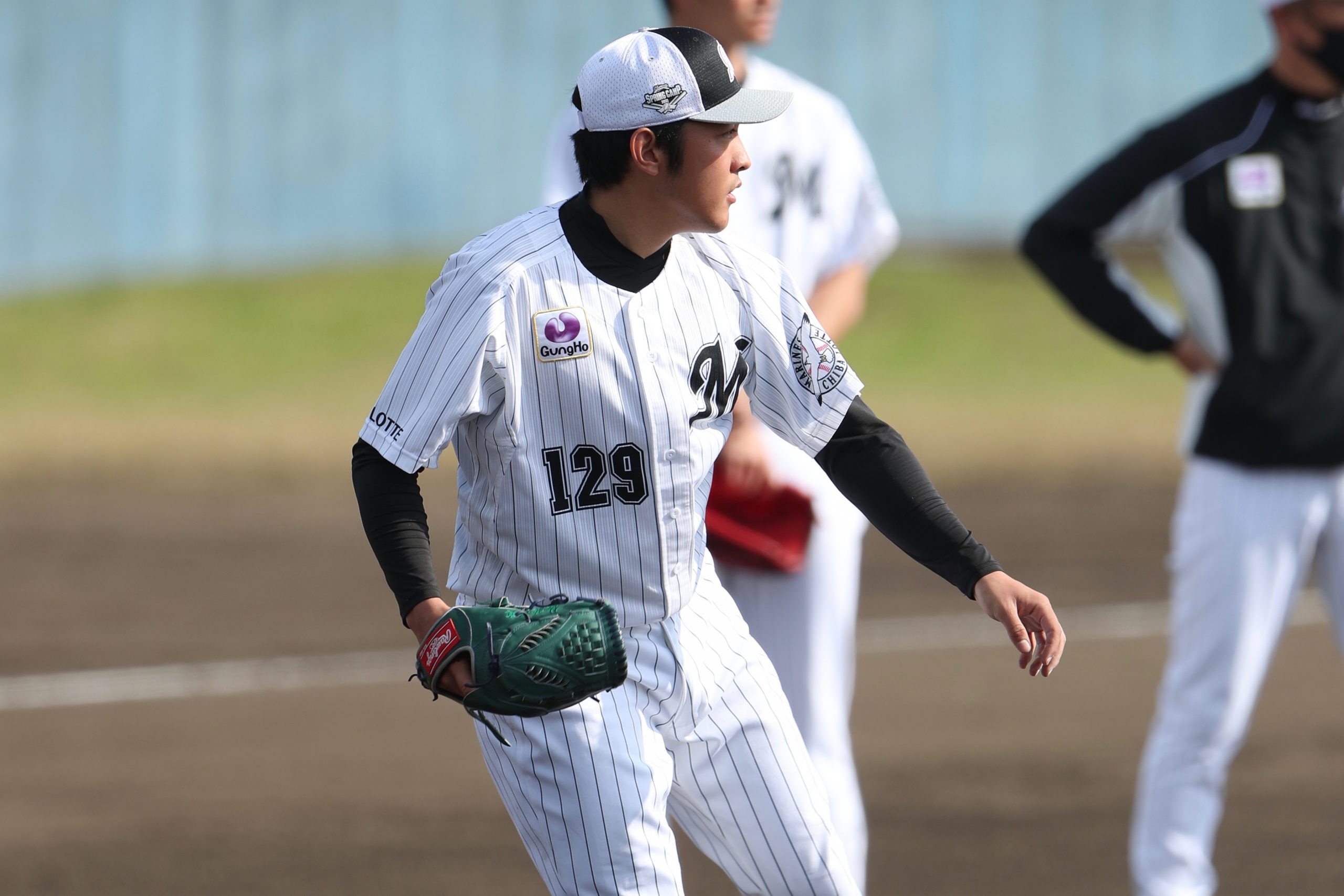◆ 第2回:明暗を分けた5番から7番
6戦すべてが2点差以内(5試合は1点差)の接戦となった今シリーズ。
前回では奥川恭伸、高橋奎二両投手を中心にヤクルト投手陣の急成長を取り上げたが、今回は打線に焦点をあててみたい。
今シリーズのチーム打率はヤクルトが「.213」に対して、オリックスは「.240」と数字上は上回っている。
それでも、両軍の投手が良いので多くの得点は望めない…。
要は数少ないチャンスをいかにしてモノにするかだ。
短期決戦における打者に対する鉄則には、「主砲を抑えるか、もしくは分断する」「ラッキーボーイを作らせない」「調子の悪い選手は最後まで眠らせる」などが挙げられる。
ヤクルトは山田哲人と村上宗隆選手、オリックスは吉田正尚と杉本裕太郎選手。彼らは不動の3・4番である。
村上と杉本は本塁打王に輝き、吉田はパの首位打者で山田は100打点越えの東京五輪MVP男。しかし、このシリーズでは徹底マークにあって不完全燃焼に終わっている。
第1戦でサヨナラ安打を放った吉田も、全戦を通じては打率.222と安打製造機からは程遠い結果。
村上は2本塁打こそ放ったが、こちらも打率は「.217」。山田に至っては1割台の低打率に終わっている。
唯一、3割近い打率を残した杉本も、第5戦の3安打を除くと他の5試合では「.190」と爆発しなかった。
この観点から見ると、主砲を抑えるか、分断することに両チームとも成功していることがわかる。
では、勝敗を分けたポイントはどのあたりにあったのか…?
実は5番から7番打者の働きに大きな差があったことがわかる。
◆ 固定できたヤクルトと日替わりだったオリックス
ヤクルトは全戦を通じて、この打順にドミンゴ・サンタナ→中村悠平→ホセ・オスナをシーズンと同じく起用した。
これに対してオリックスは、初戦にT-岡田→安達了一→ランヘル・ラベロで臨むが、第2戦ではラベロ→スティーブン・モヤ→紅林弘太郎にオーダー変更。
第3戦以降も猫の目のように顔ぶれが代わり、最後まで固定することは出来なかった。
結果はどうか…?
サンタナは2本しか安打を放っていないが、その2本が本塁打。第3戦で7回に逆転2ランでヒーローになると、第4戦も先制ソロでチームに勢いをつける。
また、この試合ではオスナが決勝打を放ち、チームの全得点を叩き出して接戦を制した。
シリーズのMVPを受賞した中村は、打率.318で脅威の6番となり、オスナも3割近い高打率を残している。
対するオリックスは、T-岡田が全戦で3安打だけ。ラベロと安達は不振でシリーズ途中から先発メンバーを外れた。
それでもモヤは初戦に代打で一発、アダム・ジョーンズも第5戦で代打決勝本塁打と気を吐いたが、いずれも活躍は代打の場面に限られて、下位打線のテコ入れとまではいかなかった。
シーズン中と同じ働きを見せたヤクルト組は、6番の中村がキーマンとなっている。
山田と村上が不発に終わっても、サンタナに一発の怖さが残る。さらに中村が「つなぎ」の打撃をできるから、7番のオスナまで生きる。まさに打線が「線」となっているところにこのチームの強みがあった。
◆ 吉田正のケガと助っ人の働きどころ
逆にオリックス打線は、迫力不足となるいくつかの要因が重なった。
ひとつはシーズン終盤に右手尺骨を骨折した吉田正が、本来の定位置である左翼に就かず、1~2戦は指名打者に回ったこと。これにより、外国人選手の起用が限定された。
ふたつ目は、セの本拠地で指名打者が使えなかったことにより、T-岡田とモヤの併用が難しくなった点。これで下位打線の迫力不足が露呈された格好だ。
ちなみに全6戦中、ヤクルトの5~7番で3安打以上を記録したのが4試合あるのに対して、オリックスは同打順では第5戦の1試合のみ。いかに打線がつながっていたか、いなかったのかを物語る数字である。
前年までシリーズ4連覇を果たしたソフトバンクには、外野を守れるジュリスベル・グラシアル選手が不動の4番として活躍した。
守りもできる助っ人と、「DH」もしくは「代打」でしか働き場所のない助っ人の差が明暗を分けた決戦でもあった。
実に9年ぶりの日本一をセ・リーグにもたらしたヤクルトでは、複数年契約のオスナと新たに来季契約を結んだサンタナが意気揚々と帰米した。一方のオリックスでは、モヤとジョーンズの退団が決まっている。パ・リーグだけならDH専門でも通用するが、日本一を手にするには打って、守れる選手が必要となる。
若手に楽しみな人材の多いオリックスに新たな課題が明確になった。
文=荒川和夫(あらかわ・かずお)