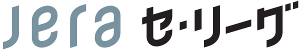セ・リーグは14勝9敗1分の阪神が、2位広島に1.5ゲーム差をつけ、首位に立っている。
藤川球児新監督の下、チーム防御率2.36を誇る投手陣もさることながら、巨人に次ぐ83得点を叩き出している打線もチームが好調な要因の一つだろう。
特に今月中旬から4番に定着した佐藤輝明が、セ・リーグ単独トップの8本塁打を放つなど、いよいよ覚醒の兆しを見せている。
巨人の岡本和真が1本差の7本塁打で直後につけているが、3位で並ぶ4人とは5本の差がある。ケガなどがなければ、自身初のタイトル争いに加わる可能性は高そうだ。
セ・リーグは2020年以降、岡本と村上宗隆(ヤクルト)のどちらかが本塁打王に輝いてきた(21年は2人が39本で並び同時受賞)。そのうちの一人、村上は今季まだ1試合に出場しただけで、復帰のメドもまだ立っていない。そんな状況だけに、佐藤としてはまたとないチャンスといえる。
ただ、そんな佐藤に立ちはだかるのが、広い甲子園球場である。阪神からは長らく本塁打王が生まれていないのは周知の事実で、最後の本塁打王は、1986年のバースまでさかのぼらなければいけない。
バースといえば、ファンから“神様、仏様、バース様”と崇められ、85~86年に2年連続で三冠王に輝いた球団史上最強助っ人である。
ただ、当時の甲子園にはラッキーゾーンがあったこともバースはじめ阪神の打者を後押ししたのも事実だ。その証拠に、ラッキーゾーンが撤去された後の甲子園は投手有利な球場に様変わりし、今に至る。
ライトからレフト方向に強く吹く浜風は、多くの左打者からホームランを奪い取ってきた。佐藤自身も遠い外野フェンスと浜風に阻まれてきた“被害者”の一人である。昨年末の契約更改の席で、佐藤はラッキーゾーンの復活を球団に要望したほどである。
さらに昨季から続く「投高打低」の傾向も終わる兆しがない。そんな環境下で、もし佐藤がバース以来39年ぶりの本塁打王に輝くことになれば、その価値は計り知れないだろう。2年ぶりの日本一奪取にも大きく近づくことは間違いない。
ただ、佐藤がもし大幅な成績アップに成功すれば、メジャー挑戦も現実味を帯びてくる。今年3月に行われたドジャースとのプレシーズンゲームで、佐藤が豪快な一発を放ったのは記憶に新しい。少なくないメジャーの球団が佐藤を注目選手のリストに入れたのは想像に難くないだろう。
課題とされてきた粗い打撃も今季はあまり目立っていない。昨季までは、高めのボール球を強振し、バットが空を切るというのがパターン化していたが、今季はコンパクトなスイングでセンター方向への当たりが増加中。それに伴って、佐藤に対する評価もうなぎ上りだ。
もちろん今後、不調の波が押し寄せることもあれば、課題の守備難も解消されたわけではない。それでも今季、本塁打王に輝くことになれば、一気に岡本や村上に匹敵する評価を受ける可能性は十分あるだろう。果たして、セ・リーグから“第3の和製大砲”が生まれるのか。佐藤の打棒から目が離せない。
文=八木遊(やぎ・ゆう)