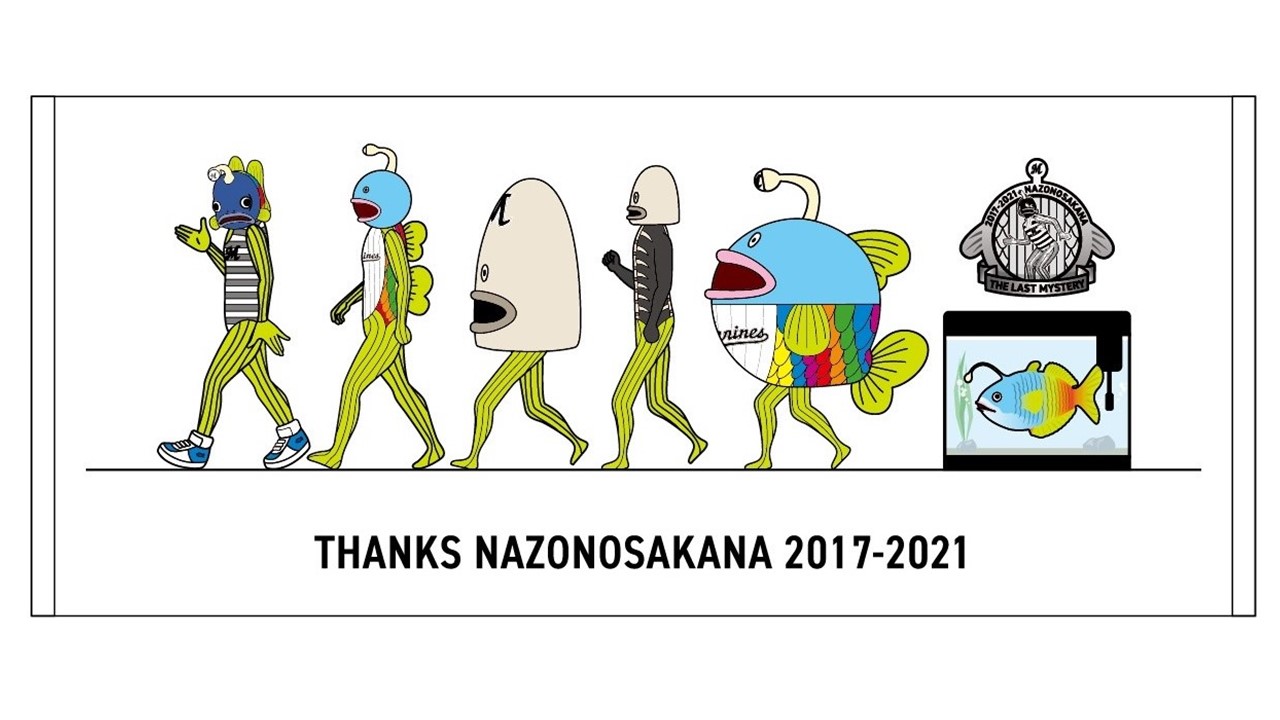◆ 第3回:チームを支えたベテランたち
史上稀に見るデッドヒートを演じた今年の日本シリーズ。わずかな差を決めたのはベテランたちの活躍だった。
ヤクルト2勝1敗で迎えた第4戦。2対1の接戦を制して、お立ち台に上がったのは41歳の石川雅規投手である。
レギュラーシーズンでは4勝5敗、ファイナルステージでは出番もなかったチーム最年長の左腕がオリックス打線を手玉に取る。6回を散発3安打1失点。しかも自責点は「0」でシリーズ初勝利を手にした。41歳10カ月での白星は1950年毎日(ロッテの前身)の若林忠志以来71年ぶりの記録として話題を呼んだ。
150キロを超す快速球が当たり前の時代に、ストレートは130キロほど。多彩な変化球で打者を翻弄する投球術が持ち味だ。
この一戦では、オリックスの主砲である吉田正尚、杉本裕太郎選手との「青山学院対決」が注目されたが、後輩を5打数ノーヒットに抑えて勝利に結びつけた。
元々、低めにボールを集めて打たせて取るが、ゲームを通じて高めへの配球割合は、わずかに7.8%で低めが62.3%。特に両雄には高めを1球も投げずに料理している。短期決戦での一発は禁物、周到な準備と確かな技術が光った。
◆ 経験と技の殊勲打
高津臣吾監督が石川と並ぶ投打のリーダーと信頼を寄せる青木宣親選手は39歳だが、プレーぶりは若い。第2戦では好投のオリックス・宮城大弥投手から決勝の中前打を放って存在感を発揮した。
メジャーを経て古巣に戻った大ベテランは今でも攻撃中はベンチ最前列で大声を張り上げている。ナインに訴えたのは心の強さだ。おとなしいチームに「もっと感情を表に出す。喜ぶときは喜び、悔しければもっと悔しがればいい」と戦う集団の心構えを説いた。今では村上宗隆選手がそれを実践している。グラウンドでもベンチでも率先垂範の長老がいれば、チームは変わっていく。
第3戦でも33歳の石山泰稚投手が好救援で勝利。そして最終第6戦も試合を決めたのは「代打の神様」川端慎吾選手のひと振りだった。こちらは、34歳の16年目。かつての首位打者は相次ぐ故障から代打稼業に回っているが、勝負強さは今も変わらない。
延長12回二死一塁から相手バッテリーミスで塩見泰隆選手が二進、最後はオリックスの6番手・吉田凌投手のスライダーをしぶとく左前に運んだ。
青木の一打も、川端の日本一を決める決勝打も共に詰まり気味のポテンヒット。相手投手からすれば、打ち取った感覚だろう。だが、青木の一打は宮城の内角球に差し込まれながら、ミートの瞬間に左手を押し込んだから中前に運んだもの。川端も内角に食い込むスライダーをコースに逆らわず逆方向に打ち返している。ベテランならではの経験と技が詰まった殊勲打だった。
◆ 見事なハーモニー
奥川恭伸に高橋奎二。オリックスには山本由伸、宮城と若手で素晴らしい素材の投手が今シリーズを息詰まる白熱の戦いに導いた。だからこそ、大量得点は望めない接戦の連続となったが、苦しい戦いほどベテランの味は生きる。
オリックスでも42歳の能見篤史コーチ兼任投手が投げ、この12月で40歳を迎えた比嘉幹貴投手が1勝1ホールドと気を吐いている。37歳の平野佳寿投手もクローザーとして持ち味を発揮したが、主役の座はヤクルト勢に譲った。
ベテランたちの役割は多岐にわたる。ヤクルトには、まだ内川聖一(39歳)、嶋基宏(37歳)らの長老格もベンチでにらみを利かしている。
2度の首位打者の実績を誇る内川は、若手の手本として打撃のアドバイスも欠かせない。村上が「影の監督」と呼ぶ嶋はチーム一のモチベーター。試合前の円陣では常に士気を高め、まとめ役として唯一無二の存在だ。彼らのような他球団からの移籍組でも、アットホームな雰囲気で迎え入れるチームの土壌があるから一つにまとまるのは速い。
プロの軍団とは18歳から40代までが寝食を共にする。指導者を含めればもっと広い年代の集合体である。野球に対する考えや取り組み方も違う。しかし、今季のヤクルトはベテランから中堅、若手までが見事なハーモニーを奏でた。それを「全員が繋ぐ野球」として引き出した高津監督の手腕が光る。
「誰とでも気兼ねなく話の出来る空気がウチにはある」と塩見は語る。
悪い時はぬるま湯の仲良し集団。それを脱却した先に日本一があった。
文=荒川和夫(あらかわ・かずお)