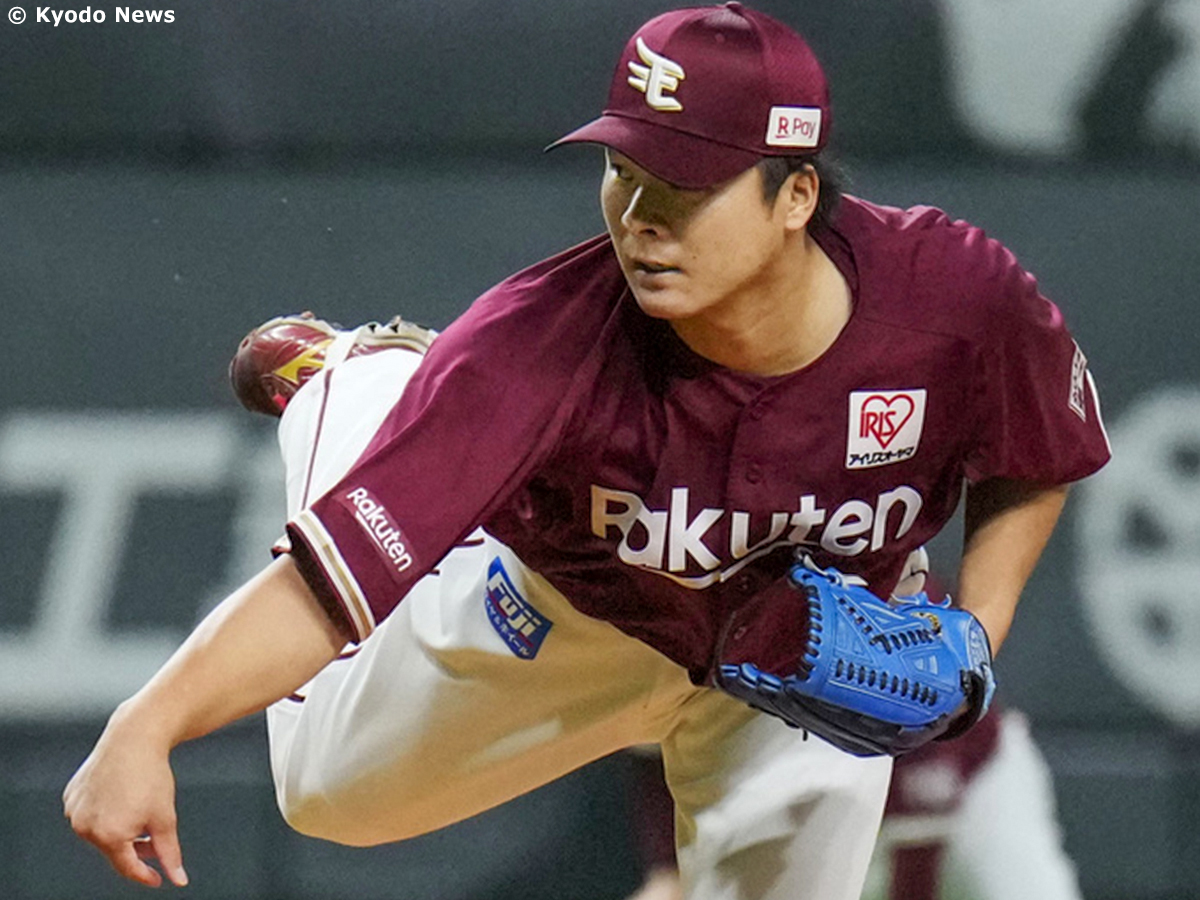◆ 第34回:育成から支配下へ…突然の一軍デビュー
一軍デビューは突然だった。ヤクルトの赤羽由紘は、8月6日のイースタンリーグ・巨人戦に出場予定だった戸田からユニフォームのままタクシーに乗り込んだ。この日、一軍のナイター(巨人戦)が行われる神宮球場へと向かっていた。
7月29日に育成から支配下契約となったばかりの22歳。神宮に到着してすぐに高津臣吾監督と会い、「スタメンだぞ」と告げられた。赤羽は「訳もわからない感じ。頭の整理もついていないような感じだった」と振り返る。
主砲の村上宗隆が「特例2022」によって出場選手登録を抹消。代替指名選手として一軍に昇格し、「7番・三塁」でスタメン出場を果たした。2回に訪れたプロ初打席は、初球、2球のストライクを見逃し。持ち味である思い切りの良い打撃を披露することなく空振り三振に倒れた。
「いざ打席に立った時はいつもと違うような自分だったんじゃないかなと思います。ちょっと後悔が残る一打席だった。もっとアグレッシブにできればと思いました」
5回の第2打席は同じ長野県出身の巨人・直江大輔から頭部に死球を受けて出塁。犠打で二塁へ進塁すると、塩見泰隆の適時打で本塁に生還。プロ初得点を挙げたが、この回でベンチへと退いた。
「一軍のああいう舞台で普通にプレーすることがどれだけ大変かということを自分の中でかなりわかりました。たくさんのファンの方に見られて、(ファームと)違う緊張感があった。これが一軍なんだ、と思った。スタメン(発表)の際にかなり拍手をもらって、鳥肌が立ちました」
3ケタの背番号「023」から「71」へと変わった。支配下契約が決まってもあまり実感が湧かなかったが、この日初めてその意味を感じ取った。
7月23日のフレッシュオールスターでは史上初のサヨナラ本塁打を放ちMVPを獲得。8月1日にはプロアマ記念試合で代打本塁打と、大舞台での強さを印象付けた。「人生の中での大きな変わり目」を感じたという赤羽。スワローズファンからの大きな拍手は、将来へ向けた期待の高さを物語っていた。
◆ 「ここからが本当の勝負」再び一軍へ
「やっとスタートライン。ここからが本当の勝負」。支配下契約が決まったとき、池山隆寛二軍監督やファームの首脳陣からは、共通してこんな言葉をかけられた。1学年上の村上からもLINEでメッセージが届いた。
やっとスタートラインに立っただけ。赤羽自身もそれを十分に理解している。だからこそ、その先を目指す。今回の一軍帯同は2日間のみに終わった。8月8日に一軍登録を抹消されたが、再び一軍へ上がるためにファームで奮闘を続けている。
試合前は、左手の使い方を確認しながら練習する姿があった。宮出隆自打撃コーチ、畠山和洋打撃コーチから熱心に指導を受ける。スイングの際に左肘が抜けて球をつかまえきれないという癖を克服するのが狙いだ。
その悪い癖を修正することで、ヘッドが返り「きれいに右中間とか、少し遅れてもライト方向へも打球が伸びていく」と話す赤羽。努力は8月14日のイースタン・ロッテ戦(戸田)で結果となって表れる。プロ入りして初めてとなる1試合2ホーマー。延長11回には試合を決める右中間へのサヨナラ本塁打を放った。
この日は、寝かせて構えていたバットを立たせ、手首のサポーターを右手から左手に付け替える作業も行った。さらに、バットは同い年の濱田太貴からもらったものを試してみた。自分の感覚も信じながら、日々試行錯誤して試合に臨んでいる。
守備面でも、内外野どこでも守れる特長を生かし、グラブにもこだわりを持ち始めた。チームの先輩である吉田大成からもらい受けた緑色のグラブがしっくりきた。セカンドやショート、サードでも使用でき、フレッシュオールスターから使い始めた。このモデルを基に新たなグラブの発注を決めた。
「いつ上がってもいいように二軍でしっかり準備して、一軍に行っても困らないように、準備という部分で怠らないようにしていきたい」。この言葉通り、一軍が優勝争いを繰り広げる中で再びチャンスをつかむつもりだ。
「数少ない中でチャンスを拾うことで、自分の野球人生も変わっていく。1球1打席で人生が変わると思っている。ファームにいるときから、1打席、1球をムダにしないように常日頃やるのが大切なんじゃないかと改めて感じました」
一軍デビューを経て呼び起こされた野球へ対するひた向きな思い。一軍でレギュラーを奪い取るため、「自分の中ではどのポジションでもいける」と、強い気持ちで挑む。活躍する場はもうファームではない。神宮の歓声が、赤羽を包み込むはずだ。
取材・文・写真=別府勉(べっぷ・つとむ)